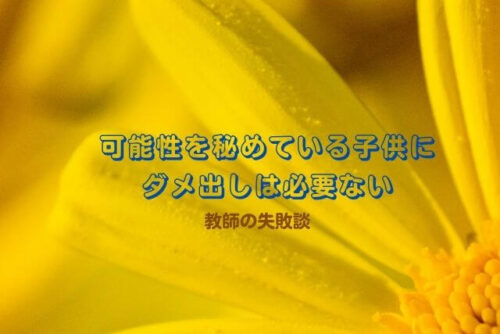セカンドイヤーを進められたご父兄の方いますか?
皆さんの中に、Term2が終わるころ、幼稚園の担任の先生から
「来年度プレップへ行かせずに、もう1年幼稚園の4歳児プログラムに通わせた方がいいのでは」というような話をされた方がいるかもしれません。
初めてそんな話を聞く親御さんは

「ええー、幼稚園をリピート、小学校のプレップクラスに他の子のように上がれないって、落第?」
とショックを受ける方もいるかもしれません。
幼児教育の現場では、‘Repeat’という言葉はあまり使わず、
’Giving an another year’ =成熟するためにもう一年待ちましょう
という言い方をします。
その方が聞こえが少し柔らかいので。
’Second year of funded Kindergarten’についてはオーストラリア人の家庭でも、毎年悩むご父兄が多いです。


この記事は、幼稚園の2年目を申請する(以下セカンドイヤー)かどうか
悩んでいる親御さん、または
オーストラリア人のママたちとの会話でこの話題について聞いて、
よくわからなかった方へ向けてお届けします。
同時にもしお子さんが、
日本でいう早生まれにあたるお誕生日(年明け1月から学年齢を 決めるカット日4月30日までに当たる場合)、自分の子を4歳でプレップに入れるか、
それとも一年遅らせて 5歳になってから小学校に上がらせるかは、
この国では、親のが希望と判断で決められるのです。
この記事でその判断に役立つよう説明していきます。
どんな時にもう一度幼稚園をやった方がいいのか?
結論から言うと、幼稚園をもう一年やるかどうかは、
子供のアカデミックな学力、知能、知的能力とは
一切関係がありません。
じゃあ、何が目安になるかというと
子供の総合的な成熟度、
全体的にみて成長の度合いが小学校教育を始められるだけのレベルに達しているかどうか
という判断です。
4歳の子供は小学校のプレップに上がる一年前に、
州の教育省から公式な幼稚園プログラムを行っている幼稚園で、
ビクトリア州の教育省から、幼稚園教育を受ける補助を受けています。
セカンドイヤーの打診が担任の先生から来た子供は、この補助をもう一度申請することになります。



セカンドイヤーの補助を申請するには、
*担任の先生が総合的に、子供の発達と学びをきちんとした査定
*親御さんと十分に話し合いを済ませ、子供を一年遅らせてプレップを始めると同意している。
*プレップ入学を考慮してみたが、その選択よりも、
もう一年幼稚園で学ぶ方が子供にとっていい判断である。
という内容を証明する書類が必要になります。
(大量の書類を幼稚園教師が準備しなければなりません。😢)



うちの子は、日本語がメインで、英語が上手く話せないので
学校へ行かせるよりも、もう1年幼稚園に行かせた方が安心だから…
というような理由では補助を受けることはできません。
5-6年前までは、この判断基準がわりと緩めで、
幼稚園の先生の主観と親御さんの希望で
「ちょっと他の子より発達が遅めだし、追いついていっていないようだわ」という様子が見られたら、
セカンドイヤー申請をすることが可能な時代がありました。
その結果、ビクトリア州の教育省が負担する、
一人当たりの幼稚園教育助成金が急増加し、
結果、きちんとした判断基準が設けられたのです。


セカンドイヤー申請の判断基準とは?
セカンドイヤーの判断基準は、きちんとした評価方法があります。
ビクトリア州の教育省が‘Does my child need a second year of kindergarten?“
ご父兄あてに説明していますので、
詳しくは下記のサイトを見てみてください。


幼稚園の教育要領の中に、個々の発達と学びの状態を査定する際に
基準にする5つ分野がカテゴリー化されています。
- Identity – the child’s sense of identity 子供自身の内面、気質
- community – the child’s connection with and contribution to their world 協調性、社会性など
- wellbeing – the child’s sense of wellbeing 感情のコントロールや身体的発達
- learning – the child’s confidence and involvement in learning 学びへの姿勢、学ぶ意欲をもっているか
- communication – the child’s communication 言語理解そして、コミュニケーション能力
ここでは、一つ一つは説明していきませんが、
この5つの分野の中で2つ以上に遅れや問題があると担任の先生が判断した場合、
セカンドイヤーの申請を勧められます。
実際に問題になってくるMaturity-成熟度とは?
簡単に表現してみると、
子供が、先生や補助の先生ら大人の援助なしで、集団生活の中でお友達とうまく遊べるか、
交渉したり、問題が起こったときに、解決していく力があるかなどが成熟度を測るポイント。
先に、説明したように字が書ける、数を数えられる、簡単な単語が読めて本を読み始めたなどの
知的能力は一切関係ありません。
そういうことは、学校に入ってから習ってきたり、お家でも、訓練すればできないことではありません。
例えば、幼稚園のような集団の中で…
- お友達のボディーランゲージが読めない、周りの様子から判断できない。
- お友達の意見も聞いて交渉や協力ができるようになってくるのが4-5歳時ごろの子供なのに、
まだ3歳児のように自己中心的で、自己主張ばかりしている。 - お友達が面白い、一緒にやろうと意気投合するような場面でも、
(発達が遅めで)共に遊ぶ社会性などのスキルが未熟で、一人で遊んでいることが多い。 - グループでお話を聞いたり、皆で同じテーマについて話し合っているときに、
話についていけなかったり、20分ほどのグループ学習でじっと座っていられず、歩き回わり始めたり、
手遊びやほかのこの邪魔になるようなことを始める - 幼稚園の先生が用意した、意図的な学び、プログラム、ゲームなどを避けて自分の好きな遊びだけに熱中する。
(一つの遊びに熱中することが悪いのでなく、年齢に合わせて設定されたプログラムに取り組む姿勢、やりたい、学びたいという学習の基礎的要素が欠けている) - お友達関係でうまくいかなかった場合、自分の気持ちや意見をその場で相手に伝えたり、相手と交渉して問題解決に到達するような能力がまだみられない。
- 物事が自分の思い通りにならなかった場合でも、気持ちを落ち着けて癇癪を起さずに取り組める。
泣くようなことになっても、自分で、心を平静に戻せる、泣き止める。 - 人が嫌がっている時、悲しんでいる時、困っている時などが相手の表情、しぐさから感じ取れて、時往々に対処できる。もっと成熟した子は、相手の感情に同感し、元気づけようとしたり、相手が笑顔を取り戻せるように場を持っていこうとする行動がとれたりする。
- お友達と遊ぶよりも、大人とだけ話したり遊んだりしたがる。同年齢のお友達の中に入っていく術を知らない。
(大人がその子のレベルに合わせてくれるので、楽だし、問題も起こらないから)
例を挙げだしたらきりがありませんので、これくらいにしておきますが、



子供の成熟度はトレーニングしても短期間で進歩するわけでなく、
乳児が一人でいつの間にかお座りできるようになったり、
歩き始める時期が人それぞれちがったりするように、ゆっくりと成長していくことがほとんどなので、
この時期に担任の先生がもし来年度の幼稚園プログラム申請を勧めるようならば、
まずは時間を話し合ってどういう理由からそれが、その子にとって良いと思うのか聞いてみましょう。
ご両親が、家庭でみる我が子と、集団の中で見る我が子の成熟度は全く違います。
ご夫婦で、また園の担任の先生と、納得がいくまで話し合って、決めましょう。
もしお子さんに障害がある場合
ここで注意していただきたいのが、もしもお子さんに自閉症などの発達障害や、
言語障害などがある場合です。
現時点で、お子さんに(児童心理学医による診断の上はっきりと診断名がついている)何らかの障害がある場合、セカンドイヤーを安易に勧めることはしません。
その理由は多くの児童心理学医や小児科医が強調しているように、
幼稚園で、週に15時間のみの教育プログラムでもう一年過ごすよりも、
週に5日通う学校とういう環境の中で学んだ方が
子供にとって良いと判断する場合が多いからです。



その場合は、小学校を通じてその子に必要な補助指導員、または、
その子供に合ったカリキュラムを小学校が準備してくれるよう、
幼稚園と学校が密に連絡を取り合い、来年度2月からの新学期に間に合うように準備します。
‘Transition Report’というレポートを、幼稚園の先生は州の教育省で用意されたオンラインんのポータルで個々のサポートになるよう準備します。Term4に各小学校へ送ります。このレポートについては、また別の記事で書きます。


英語でうまくコミュニケーション取れない子供
これを読んでいらっしゃる親御さんの中に、
お子さんの英語でのコミュニケーション能力について悩んでいらっしゃる方がいるかもしれません。
もし、日本語でも、話す、聞く、理解する、などに問題があるようならば、
それは言語能力(コミュニケーション)に遅れがあると考えるべきなので、
その場合はほかの上記の発達エリアで他にも問題があるかどうかを総合的に考えて判断基準にするべきです。
セカンドイヤーをするかどうかはいつまでに決定しなければならないのか?
タイミングとしては、Term3の最後にははっきりとした回答を出してほしいというのが理想です。
ほとんどの小学校が、Term4初めに、
来年度のプレップ入学児を集めて、3-5回ぐらいに分けてオリエンテーションを始めるからです。



Term3の間に担任の先生としっかり話し合い、
セカンドイヤーを申請する場合と小学校へ上がる場合のメリットデメリットを含めて、決断できるようにしましょう。
他の先輩ママたちに話を聞くのも、一つの手です。
まとめ
幼稚園のセカンドイヤー(2年目)を申請するかどうかという問題は、
画一的に、年齢で小学校へ一斉に上がるシステムで育った日本人にとっては馴染みのないシステムです。
割合的に言えば、毎年1クラス30人いたら大体2-3人は申請することになるのが普通です。
ですから10-15%ぐらいの割合が一般的です。
たまに、幼稚園2年目の申請の話が持ち上がると、
落第の烙印を押されたと勘違いしてがっかりするご父兄や祖父母を見かけることがありますが、
子供の発達にあった学年で学ばせることがいかに大事かを考えて、
そこにポイントを置いて話し合われることをお勧めします。
あくまでも一般論で書いていますが、
子供一人一人、ケースバイケースで2年目を申請した方がいい場合と、
小学校へ上がった方がいい場合がありますので、一概には決められません。
学校へ上がるということは向こう1年の将来を見据えるのでなく、
高校を卒業するまで最低でも向こう13年の学校生活について決めるということになります。
焦らず、よくご家庭で話し合って決められますように。





もし上の説明を読んでも、まだ迷っている、悩んでいるという方がいましたら、お問い合わせを通じてメールで質問をください。
ご相談に乗れるかもしれません。