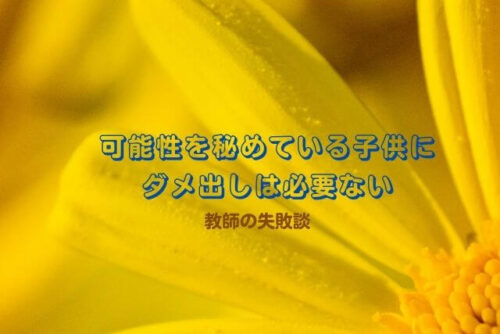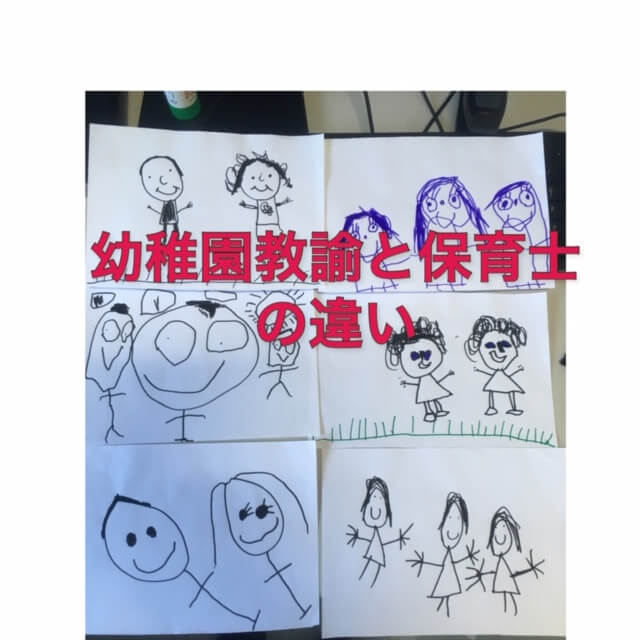皆さんは、
という話を聞いたことがありますか?
年齢で自動的に次の学年へ上がらせずに(つまり、小学校のプレップに入学を見合わせて)
子供の発達、成長に合わせて、2年間の幼稚園教育をする方法があります。
別の記事で、セカンドイヤーについては既に詳しく説明しています。
日本にはないシステムなので、興味のある方はこちらからどうぞ。

ビクトリア州では熟知されているシステム
2021年度コロナ対策で外出禁止令、自粛などに揺れたビクトリア州。
コロナ対策の会見で、ビクトリア州知事がコロナ対策のStage4の自粛を延長する発表をした際、
教育省のトップに対して、記者が
”コロナで殆ど、幼稚園に登園できず、
本来の発達や、スキルの向上が得られなかった
子供たちはもう一年、セカンドイヤーで幼稚園をやった方がいいのか?”
という質問が、ちまたで出ているが、これについてどう思うか?
という質問をしていました。
これについては、はっきりと、ビクトリア州教育省が、
上記の説明、”発達、成長の遅れ”と聞くと、親としてはギクッとすると思いますが、
要するに、子供が5歳で、年齢的には学校へ上がる歳だけれども、成長のあらゆる面で
少しゆっくり目で、他のお子さんと比べてワンテンポ遅め。先生の言っていることも、
分かっているのか、分かっていないのか?
自分で、先生の言っていることに従って、遊びや学びを選んだりすることに、少し
疑問がある… という場合、幼稚園の先生と親が相談して、翌年に、小学校へ行かせるか
それとももう1年、ビクトリア州から幼稚園教育を受ける補助金を申請して、
進級するのを1年延ばすというシステムです。
(詳しくは上記の関連記事を読んでいただければ、分かりやすいかと思います。)
ご父兄とこの大事な進路を決めるのは、Term2の終り頃で、
確実な決定をする時期は、Term3の間です。
私も、毎年、このご父兄との面談をする前には、しっかりと子供の発達や成熟度を観察して、
教師としての判断と、意見を伝えることができるように、準備します。
 Miku
Miku巷では、熟知されているシステムなので、ご父兄の方から、
「セカンドイヤーを申請して、もう1年幼稚園に行かせたい」と、
打診してくるかたもいます。
クラスの10%強はセカンドイヤー予備軍


毎年、30人子供がいたら、大体10%強は、
セカンドイヤー予備軍になります。
つまり、発達、情緒、社会性、学び、言語などに遅れがあり、
小学校へ上がったとしても、もしかしたら、小学校で
”学年をやり直す”ことになりかねない子供たちが、予備軍になります。
”学年をやり直す”って、つまり学校が子供を進級させないことです。
幼稚園で、アップアップしながら、
他のお友達の遊びや、会話にようやくついていけているか、
いけていないかのレベルにいる子供は、
無理に親の希望で小学校へ上がっても、
その発達や社会性の差は、縮まることなく、かえって広がり、
お友達からも孤立して、ずーっと18歳の学校生活を終えるまで、
敗北感に打ちひしがれて、大事な人間としての自信を失ったまま、
大人の階段を上がってしまうケースも多いです。(経験から書いています)



教師としては、明らかに進級を薦めず、もう1年幼稚園をするべきだと考えますが、
親は(厳しい言い方になりますが)、
世間体や、エゴ、楽観視から、現実から目をそらし
無理に小学校へあげようとする方もいます。
親が決定権を持つ
結論から申し上げますと、
自分の子供を小学校へそのまま進級させるかどうか、
最終的に決めるのは親御さんです。
いくら、幼稚園の教師が薦めても、



小学校の校長先生が
「幼稚園の先生は何と言っていますか?
先生が薦めるならば、セカンドイヤーを申請しることをお勧めします。」
と、説得しても、親が、どうしてもいう場合、誰も法的には止めようがありません。
幼稚園教師と親との信頼関係
自分の子供が、他の子供たちと一緒に進級できない。
もう1年、幼稚園でいろいろな体験を学ばせて成長してから学校へ行ったらどうでしょう?と、
言われても、戸惑ってしまう、親御さんの気持ちも、分かります。
私は、毎年、セカンドイヤーの話を持ち出す前に、
まず、ご父兄との信頼関係をできる限り築いて、
お互いに子供にとってベストの判断がつけられるようオープンに話ができるように
努めます。



「来年度の話ですが、ご両親としてはお考えでしょうか?
OOちゃんを見ていて、~ところがあって、このまま小学校へ上がるのに
は少し不安な点が多いのですが…」
みたいな話を持ち出す機会が来ても、



「実は、私たちも少し問題があることに不安は感じていました。」とか、
「先生がプロですので、先生の判断にお任せします。」
というような回答が返ってきて、両者とも意見が同意することが多くなります。



「私は、きっとそのうち追いつくとおもいますが、主人に相談してみます。」とか、
「まだ4歳ですよ。今から何が分かるんですか?」
😣というような、あからさまな拒絶反応は避けられるわけです。
【実例】後悔しても遅かったという親の本音
今は大学生の息子がPrepだったころ、週に1日、
学校のクラスのお手伝いをしていたことがありました。
学校では、先生が一人で24~29名ほどの生徒を担任するので、
学習レベルの全く違う子供たちの指導を仕切れない部分があり、
本読みを一緒にしてあげたり、ゲームをしながら、算数の学習をしたりする親のヘルパーを積極的に使っています。



その時、見たのです。😲
一クラスにいる子供たちの中にハッキリと、
学習態度、レベル、成熟度、理解度の格差が
ものすごいという現実を。


こちらの学校は、画一授業でなく、小さなグループに分かれて、
算数のゲームだとか、本読みだとか、サイコロを使ったゲームだとか、
幼稚園の延長のような ”Play-based Learning”です。
楽しく遊びながら学べるという小さい子供の発達にあった学習法になっています。
が、その学習をやっているはずの間に、
やれ鉛筆を取りに行くといって、廊下のカバンのあたりをうろうろしたり、
机の下にもぐってふざけていたり、お友達がふざけていたら、
やるべきことをそっちのけで一緒になってどこまでも脱線してしまったり。
幼稚園児が、小学校のユニフォームをきてお部屋にいるような感じでした。
担任の先生に、OO君って…と授業終了後に話をすると、
先生も私が教師であることを分かっているので、ぶっちゃけた話をしてくださって、



一人で学べる基本的なスキルが、未修得の子供たちが、
小学校へ入ってきているので非常に困っている…
ということでした。
もちろん、私は教室内で見たことを、吹聴したり、自慢げに話すこともしませんでしたが‐
注:学校側も、そういうキャラのご父兄には第一にクラス内のヘルパーはお願いしないようです。子供のプライバシー問題もありますので
その子供たちの親ごさん達とたまたまの会話中、さりげなく幼稚園時代の話を聞いてみると…



幼稚園の先生には、もう一年幼稚園に残った方がいいと言われたけど、
当時は、そこまで真剣に考えていなかった。
Gapは成長するうちに、埋まっていくと思っていた。



私は、セカンドイヤーに賛成だったけど、祖父母が
”何も、うちの孫に限って遅れているところなんてない!” と、
かんかんだったから、仕方なく、他の子供と一緒に小学校へ上がらせた。



主人が、”自分の息子に限って、遅れなんかあるわけない、
一体どんなつもりでその先生は発言しているんだ!
子供のことを一番わかっているのは、私たち親。
先生の言うことなんて気にかけなかった…
本音で答えてくれた親、ほぼ全員が
幼稚園の先生からセカンドイヤーの打診を受けているにも関わらず、
断って無理やり学校へあげた組でした。
そしてほぼ全員が、無理に進級させたことを後悔していました。
理由は、学習面だけでなく、
生活態度、お友達関係、全てにおいて問題が生じていたからです。
子供自身が、週に5日間、楽しく学んで行ける段階に達していなかったのに、すぐに
追いつくだろうという見込み発進で、進級させてしまった結果です。
親同士という立場で話すと、自分が見栄を張っていたことを、認める人も結構いました。
学習面だけでなく、友人関係にも大きく影響
私自身の息子が高校生になるまで、
いろいろな学校生活の話を聞いてきましたが、
子供の発達の未熟さは、
お友達間でも大きな問題になることが分かりました。
幼稚園で必要なスキルを習得できていない子供たちは、
学校に上がるとお友達同士で、
うまく溶け込めない、
仲間に入れてもらえないという問題に
発達することが多いのです。


もう、小学校3年生ぐらいのキャンプに行く前なんかは、
子供たちの判断から見ても、未熟でお友達関係を維持するスキルが身についていない子は、
1人だけお泊りグループに入れてもらえなかったり、一緒に行動するバディを探せなかったり。
3年生の時に、課外活動へついていく役が回ってきて、子供同士の行動を観察していたら、
もう、子供間の力関係がすぐ見えました。😢
子供に「OO君、お友達がいなかったみたいだけど..」と聞くと、



「OO君は、いつも真面目にしないといけないところでも
すぐにふざけて、幼稚だから」とか、
手厳しい発言、観察力を語ってきていました。
その子もやはり、幼稚園から、他の子供とのGapがあって、
ずーっと、高校卒業するまで問題を抱えていったことを
子供の発言から思い出します。



このようなケースは、1人だけでなく、
何人も見たり、聞いたりしています。
親御さんは、”成長のGapはいつか縮まる”と考えていても、
自分の子供同様、他の子供も成長するので
Gapはより一層、広がっていく
ということが、息子の友人仲間を見ていて感じました。
今後15年間続く、学校生活について長期で考える
このような数々の実例をみているので、私はセカンドイヤーの話題を持ち出すとき、
真剣に親御さんと相談します。
他のお友達と一緒に、学校へ行かせたいという気持ちも、理解し、尊重しつつ。
でも、親の見栄や、世間体を外して考えて、その子供にとって幼稚園をもう1年やることの
メリットとデメリット。
学校へ上がった場合のメリットとデメリット。
総合的に判断して、一緒に親御さんと悩んで決めます。
OOちゃんが自分の子供だったら…と考えると、判断しやすくなることもあります。
小学校へ上がっても、進級できそうにない発達レベルの子供を、わざわざ、
無理に押し込めるでしょうか?
でも、小学校プレップを含めて7年間行く間、進級できない子は、



「あいつ、馬鹿なんだぜ~」
と残酷なレッテルを子供たちにはられてしまう現実があります。



「プレップをやり直すぐらいなら、もっと強く、幼稚園の先生にその現実を言ってほしかった」という声も、きいたことがあります。
子供にとっても、親にとっても、辛い現実になります。
まとめ
最後になりますが…
幼稚園のセカンドイヤーを終えてから小学校へ上がった子供の親御さんと話してきて、
後悔している人を今まで見たことがありません。
公私ともに、いろいろ聞いてきましたが、
皆、2年間幼稚園に行かせて、全体的に成長してから
学校へ上げて良かったという意見です。
反対に…
無理に学校へ上げたが故に、お友達ができず、
馬鹿扱いされ(ただ、成長がゆっくりだったというだけなのに)、
学校生活をずっと楽しむことなく、
勉強も嫌いになったというケース、実はとても多いのです。
この記事を読んでいる親御さんが、今現在のお子さんの様子だけでなくて、
長期的なスパンで、成長、学習、お友達関係も含めて、
ベストな時期に、正式に学校生活に送ることができるよう、幼稚園の先生や、
オープンに話し合えますように。