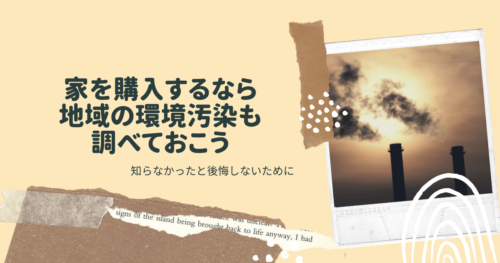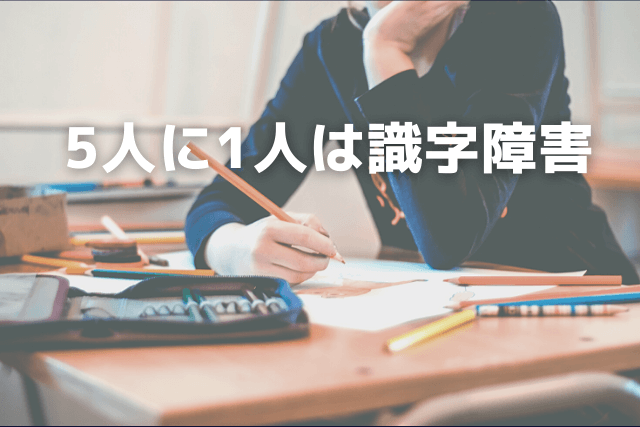オーストラリアで、普通に会社に勤め、子供の学校や、習い事、日本人の友人だけの世界で生きていたら、関わることがなかったであろう社会問題。
幼稚園の先生として、いろいろな家族と関わっている中で見えてきた、避けては通れない社会問題を、 垣間見ることがあります。
それは…
統計上、2分に1度被害者が出ているという、家庭内暴力のことです。
海外在住の日本人被害者もいておかしくない
この記事を書こうと思った理由は、私が思っている以上に、ここ、オーストラリアで家族もいない、言葉の壁もある、家庭内のことで誰にも相談できないと、絶望感にさいなまれ、孤独に陥っている日本人が思っている以上に多いかもしれないと、ブログを始めてから、感じ始めました。
家庭内暴力というと、身体的暴力のみを考える人がいるかもしれませんが、
ビクトリア州の「家庭内暴力保護法2008-SECT 5」という法によると、
下記のように定義づけられています。
家庭内暴力の定義
この法律の目的のために、(1)家庭内暴力 は-
(a)その行動の場合の、その人の家族に対するその人の行動—
(i)身体的または性的に虐待的である; または
(ii)感情的または心理的に虐待的である; または
(iii)経済的に虐待的である。または
(iv)脅迫的である。または
(v)強制的である。または
(vi)他の方法で家族を支配または支配し、その家族にその家族または他の人の安全または健康に対する恐怖を感じさせる; または
(b)パラグラフ(a)で言及されている行動を子供に聞いたり、目撃させたり、またはその影響にさらしたりする人の行動。
引用:FAMILY VIOLENCE PROTECTION ACT 2008
このように、家庭内暴力は、身体に及ぶもの以外でも、多岐にわたります。じっと耐えている人が多いせいか、表面化してこない日本人の被害者の数も多いと体験者から聞いたこともあります。
虐待を疑ったら行動することが義務化
2017年から、幼児教育業界で働く職員、特に教師は、子供に何らかの虐待が疑われる場合、 ”Child Protection”などのしかるべきサービスへ通報することが、法的に義務付けられました。
虐待を疑いつつ、何の行動も起こさない、見てみないふりをするなどした場合、違法とされて、逮捕されることになったのです。
教師への通知報告が法的に義務化された時、「どんどん、先生への責任が重くなるな」と、私はその責任の重さから、重圧感を感じましたが、ビクトリア州教育省や、年に一度の幼児教育会議などでの研修を重ねていくうち、子供の命、後からでは取り返しのつかない虐待を防ぐには、必要なことだと納得していけるようになりました。
裏を返せば、それくらいしないと、日常的に起こっている家庭内暴力は防げない、そして、あらゆる暴力を目の当たりにしてしまう子供の数が、半端なくこの国では多いという実態が、理解できるようになりました。
社会的な構造から日常化している家庭内暴力
2019年に私が出席したビクトリア州教育省とモナシュ大学が合同で開催した、幼児教育者へのワークショップがあり、そこで家庭内暴力と社会的な構造がどこから来ているのか動画を見せられました。
動画のタイトルは、Let’s change the story: Violence against women in Australia
この動画内で、
毎日657件の被害が、オーストラリア国内、ある特定の場所に限らず
どの地域であろうと起きている。
週に1人のオーストラリア女性が家庭内暴力で命を落としている。
実態があると言っています。
その背景に、大人になって家庭内暴力の”加害者/被害者”になるずっと以前に、子供のころから
“Gender Inequality (ジェンダーの不平等)”が社会的な構造として長い間存在していることが、問題の
根底になっているとも伝えています。
オーストラリアでは、こういった風潮化されている社会構造に加えて、教育の不平等、薬物乱用、貧困、メンタルヘルスなどが絡み合い、悪循環から抜け出せない、家庭内暴力にあっても簡単に子供を連れて、生活の立て直しができないような社会問題に発達してしまう現実が日々、起きているのです。
幼児に積極的に教えていく平等とインクルーシブ

これら悪しき社会風習を、次の世代へ持ち越さないために、
幼児教育では、ビクトリア州の定めたガイドラインで、
Eauity(平等) とDiversity (多様性) について、
子供たちがつね日頃から受け入れていくよう、その重要性がうたわれています。
各家庭の父兄と、尊重に基づいたパートナーシップを気づき、
それぞれの家庭、家族が持つ違いに、考慮して、大事にしながら、
子供の成長を見守ることが大切だと、”National Quality Standards (国の品質基準)でも
提言されています。
今すぐに、この絡み合った社会問題が解決されることは、容易ではないと判断できますが、
次世代の子供たちの生活が少しでも向上するように、
積極的に、日頃の保育で、子供の幼少期から、意図的に教えていかないといけないと、
国や州政府の方針が変わってきているのを感じます。
教師として何度も目にしてきた家庭内暴力にさらされる子供たち
安全な場所へ保護されたB君家族
メルボルンで幼児教育に関わり始めた初期に、
子供らしからぬ表情を全く変えないB君が、年の途中で、転入してきました。
お母さんが、何故か、いつも骨折を繰り返し、包帯を巻いて痛々しくB君の送り迎えをしていて、
それが、家庭内暴力によるものだと気が付いたのは、
B君家族が、暴力を繰り返すお父さんの元から逃げるようにシェルターへ引っ越していった後でした。
当時勤務していた保育園の園長が、

「B君は、幼少期から繰り返される暴力を目の当たりにしてきて、
怖さから、感情のスイッチをオフにすることでその恐ろしい状況に
慣れるという技を身に着けて、生活してきた」
と精神科医から報告があったと話してくれました。
B君の口内の唾液を調べたら、長期にわたってストレスを表す分泌物の ”コルチゾール” が濃く分析されたとも、報告があり、B君の表情や行動だけでなく、生体検査ではっきりと、ストレスが数値となって現れるということを知ったのは、その時が初めてでした。
急にお漏らしを始めたN君
体つきは他の誰よりも大きいのに、言語の発達に遅れがあって、
吃音もでていたし、自分の感情のコントロールが上手くいかないN君。
私も担任として、お母さんから 「ADHDの発達障害があるのでよろしく」と当初言われていました。
妙に人懐っこくて、すぐ、ペタ―っと体を寄せてきたり、
ハグをして感情表現をしてくる子供で、幼稚園が大好きな子供でした。
そのN君が、急に保育中にお漏らしを始めたのです。
私は「おかしいな…」と思って、
お母さんにそのころ何か環境が変わったりしたことがないか聞いてみたのですが、
お母さんの回答はうやむや。
でも、そのころ、N君が、「家に警察が来て、おばさんが、お母さんのことを押して」と、
断片的な話をし始めたのです。
言葉に遅れがあるので、きちんとした説明をN君から聞き出すことは困難でしたが、
後で、お母さんからそれらは全て、現実にあったこと。
お母さんと、同居する義理のおばさんが口論から小競り合いの大けんかになり、
警察沙汰になったと。
それを全て見ていたN君が、精神的なショックを受けて、
お漏らしになっているとわかりました。


N君も、お母さんと赤ん坊の弟と他州の親戚の家へ、引っ越していきました。
N君のケースでは、彼がADHDと診断され行動面でいくつか問題が出ていたのは、
発達障害という理由よりも、家庭環境がそれらの原因になっていたのではと、
私は今でも思っています。
「僕とママは死ぬことにしたんだよ。」と真顔で言ったJ君
J君家族が、経済的、薬物がらみ、貧困、家族間問題など多くの困難に面していることは、
すでにケースワーカーからの報告で、職員間に知らされていました。
J君は、自分の置かれている立場がとても特殊な状況であるとは、
もちろん知ることもなく、家庭内で目にした暴力や暴言を幼稚園で、
突拍子もないタイミングで話してくれました。
教師として、日本人としても、ほとんど耳にすることのない状況を、
それが当たり前のように話すJ君。
彼が私に話すことは、心の中にたまっている思いを外に出す、
アウトプットの必要性からだと感じて、聞く話に心を痛めつつ、
そしてその話に危険性が入っていたら直ぐ行動できるよう、
私は注意深く、聞き役に徹していました。
でも、次の言葉を言われた時は、涙がこぼれそうになりました。



「ママがね、パパに壁にボーンて突き飛ばされて、いじめられて。
警察を呼んだんだけど、今すぐ冒される危機とは判断できないからって、警察は何もできないって、帰って行ったんだよ。
だからね、ママと僕は自殺することにしたんだ。」
5歳に子供が言えることでは無いような内容でしたが、
J君は警察が来て、彼らが助けることもできず、
危険とは判断できないと言って帰って行った、
その一部始終の会話をそのまま覚えていたのでした。
そして、その後、落胆した母親が、J君にこぼした言葉も。
自殺という言葉は普通の5歳児は、聞いたことがない限り、知らない言葉のはずです。
私は、嗚咽しそうになる声を抑えて、できるだけ平静を保ちながら、J君の目を見て言いました。



「先生も、お友達もみな、J君の事、大好きで、大事に思ってるから、
簡単に死ぬなんて言わないで。
死んだらもう帰ってこられないし、皆と会えなくなっちゃうんだよ。
J君にはこれからもたくさん遊んでお勉強して、
お友達作って大きくなるまでずっと生きていってほしい。
とっても大事な命だから。絶対、助けてくれる人はいるから。」
教育が悪循環から救い出してくれるのか
担任してきて実際に見てきた子供たちのケースの、”一部を” 書きました。
担任するグループの中に、このような家庭環境から来ている子供、
発達障害のある子供、”Gifted”と呼ばれる知能がとびぬけて高い子供らを
包括的にインクルーシブ教育を行うことは、とても大変です。
一クラスの中に、数々の問題、発達障害、親から打ち明けられた深刻な家庭問題、
経済的な問題や社会問題が絡み合って、真剣に向き合おうとすればするほど、
解決ができないことに気が付きます。
教師として、頭を抱えることが多いです。
先に挙げた子供たちのケースは全て、
私たち教師が必要な対処をとり、公的なソーシャルサービス機関、
ケースワーカー、警察などと関わりデリケートに扱ってきました。
でも、最終的な身の置き場の決断は、被害者である子供の親、大抵はお母さんに任せられていて、
そのお母さんがどうしたいか。
勇気を出して状況を変えるために、家を出るとか、生活を変えるとか、
”勇気をもって強い決断”をしなければ、前に進めていけない、
生活から逃れられないような状況だったということが、共通していました。


関わってきてわかるのは、どのケースでも、被害者になっているどのお母さんたちも、
大人になるまで家庭、学校などで落胆するような扱いを受けてきていることが多かった
ことはでした。
本当に、社会的な問題は、一つのジェネレーションだけにとどまらず、
次のジェネレーションに持ち越すという統計で表れている事実を、
教師という立場からまじかに見てきて、理解できました。
オーストラリアは、家庭内暴力による被害、殺害、
そしてそれを目にする子供たちへの精神的虐待をこれ以上増やさないよう、
様々な行政が動いています。
” Child First” や、”Orange Door”といったような、
万が一身の危険を感じたら、直ぐにその場から逃げられるようなアクセスポイントとしての機関や、
女性保護のシェルターも数多くあります。
もし、この記事を読んでいる人が、または、その人の身近にいる人が、
同じような状況にあるとしたら…
誰も助けてくれない、メンタルが落ち込んで、判断力が低下している状況にあっても、
子供と自分の安全を守るために、勇気を出して行動してほしいと願っています。
そして、その行動を見ている子供たちが、しっかり教育を受けて、
違う人生を自分でつかみ取っていけるよう、私は強く願っています。