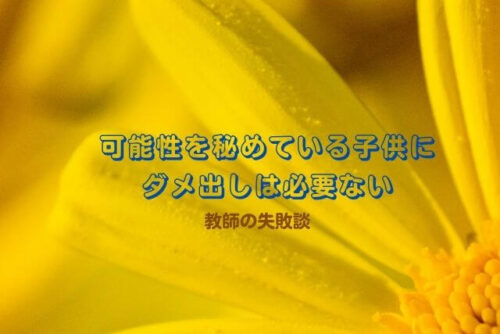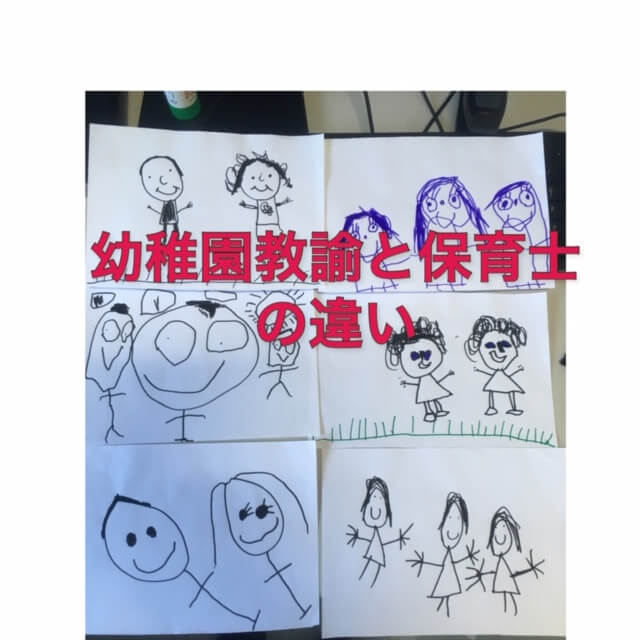50代になってもまだバランス取れず?
あっという間に過ぎた2週間の春休みが終わり、
先週の10月5日から、年度末にあたるTerm4が始まりました。
休み中は、基本的には仕事はしなくていいのですが、
やはり教師という職業上、やることリストは果てしなくあります。
年度末最後のTermに入って、仕事量に押しつぶられぬよう、少しずつでもやることリストを減らして…と思っていました。
でも、ほとんど、計画倒れに終わりました。
それくらい、体力、気力ともども疲れ切っていたせいだと思います。
他の、記事にも書きましたが、今年は、コロナの影響のみならず、
園の職員間のぎくしゃくが激しく、ただでさえ仕事量が多いところに加え、
それらの調整に追われて、自分で感じている以上に身体に影響を与えていることが分かりました。
早朝4時前に’パッと’意識が起きて、それから眠りに戻れない”睡眠障害”が出ていて、
更年期の影響もあるのかな~と勝手に考えていたのですが、
ホリデー中は、その症状が全く出ていなかったのです。
そんな’睡眠障害’など何処へ?というほど、ぐっすりと眠れていたから自分をみて、
あれ~? とびっくりすると同時に、更年期のせいでも何でもなく、
仕事からくるストレスが、睡眠障害の原因であったことを、はっきりと悟りました。
自分で第一線から降りる勇気
ここ何年も、教師としてもっと学ぼう、あれもこれもと、あらゆる研修にできる限りでて、
幼稚園教師の資格の中でも、次の”スペシャリストランク”へ上がる資格審査にも挑戦し、無事パス。
中間職として、園もまとめてやってきました。

”先生のクラスへ入るには、市役所へ希望を出せば入れますか?”
と切に、私の人柄をかって下さるご父兄もいます。
ありがとうございます。
そんなにまで、私をかってくださって。



でも、ここらで、
第一線を降りる勇気、軌道修正が必要だと感じてきています。
コロナの影響で幼稚園の閉鎖があった時(2021年ごろの話です)、
”社会的、発達的などいろいろな面で、不利益な立場にある 子供たち、特別枠で、登園を許される”
子供たちが、地域の中でどの園よりも多いことを知りました。
特別枠に入る子供たち、つまり、いろいろな発達障害や、家庭環境の問題がある子供、
一筋縄ではいかない問題が多いのが、どこの園よりも多い。
結果として、クラスの担任としての仕事量が半端なく多くなる理由がここにあると
コロナ禍のデーターで明確になったのです。
どうりで、やっても、やっても、仕事が終わらない。
一つ問題が解決したと思ったら、また別の子供の家庭や発達の問題が出てきて、
専門医から書類やレポートの提出を要求される。
これらはすべて、普通の担任の仕事プラスでやらなくてはいけない仕事となり、
どんどん仕事量で埋もれていく自分が見えていました。
私の今までの知識と経験と知識で助けられることがあったら、特に、発達障害や、育ちに遅れがある子供たちの親御さんは、どんな情報でも知りたい、教えてほしいので、できる限りのことはしたい。というのは本音です。
が、私は、特別学級の教師でなく、普通学級の教師であり、
他にも子供たち、クラス全体30人の子供たちの成長も担任として見ていく役目があるので、
全然時間が足りない。ということが、ジレンマになっていました。
ホリデー中、偶然、前任のチームリーダーとスーパーで立ち話になり、
私の背中を後押しするようなことを言われました。



「ああ、来年度の話聞いてる?
Mikuのいる園は、園児の定員増やして最高の一クラス33人にするって話。
うちの園は、人気がなくてほとんど来る人もいないから、22人までにして先生と助手二人でやることにするみたいよ~。
人気がある園は、辛いよね」



「今の定員より増員の33人になる?
市役所の入園児を振り分けるオフィサーは、実際の33人の中に、
一体何人、発達障害を持っている子供、または、発達障害の疑いのある子供の割合を知らないから、どんどん、数だけで子供を送ってくる。
私に任せておけば、上手くさばいてくれるだろう。と思っているんだな。」と、会話から絶望感に打ちひしがれました。
彼女との会話が、「自分で、これ以上はできない。
働き方を考える時がきた、第一線で働くという電車から降りる時が来た」という判断をする
後押しになりました。
どんな働き方にシフトしていくか?
アラフィフの老体に鞭打って、子供の前では、年齢を忘れているけど、
帰宅するとドドーっと疲労感。
この働き方を見直さないと、この国の現在の時点で定年になっている67歳まで持たないな~と
自分で考えていたところでした。
今、受け持っている4歳児と3歳児二つのクラスの担任から、一つのクラスだけにしようか。
まだ、バリバリ働けるはずのアラフィフで、勤務時間を減らすのは、リスクなのではないのか?
コロナで仕事を失って、失業者がわんさか出てくる社会状況を考えたら、
仕事があるだけ良しとして、まだフルタイムに近い時間で働くべきなのではないのか?などの、
心理的なブレーキも、自然にかかってきます。
一クラスになって、空いた時間で、何か別の仕事をするのか?
代理教師として、働きたい時だけ、病欠のスタッフに代わりクラスに入ることにするか?などの選択もあります。
働き方は一つでない
アラフィフって昔でいうと、
人生終わっていた年齢です。
でも私は、まだこの先、平均年齢まで生きると仮定して(そのつもりです。笑)、
アップアップしながら、仕事量に追われていかない。
”先生”という地位と、安定にしがみついているのではなくて、「自分にしかできないこと」を探して、選んで、自分らしく生きていきたいな。
それが、今なのかな。と感じています。
人生の新しいチャプターのスタートです。


こんな考えから
働く場を変えてみた!っていうのが、この記事です。
お時間のある時にどうぞ。