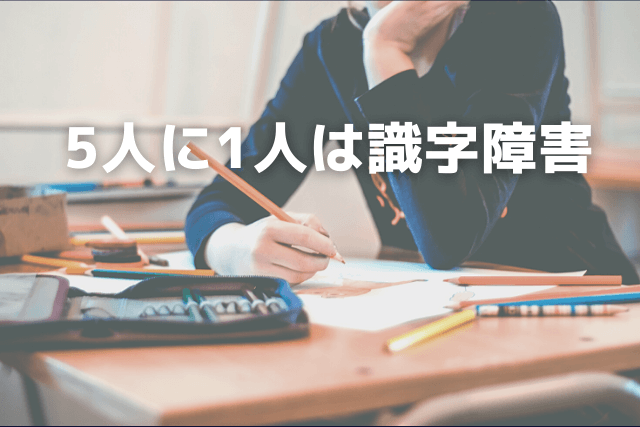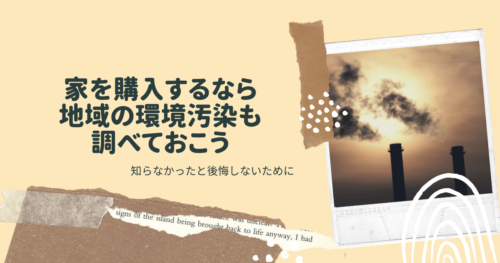オーストラリアは世界の中でも、移民者の率が高い、立派な「多民族国家」です。
それが故に、皆が同じ型にはまらず、いろいろあって面白かったり、
人生の半分をここで過ごしている今でも、
”えええ~!”と思わされることが多いのですが、
国民が平均的に義務教育を受けるのが当たり前の日本と、
確実に違うなと気づかされるところが、大人の識字率の低さです。
識字率って何?

More than one in five Australians can at most complete very simple reading or mathematical tasks, an OECD report says.
CREDIT:ERIN JONASSON “One-fifth of Australian adults have limited literacy and numeracy: OECD, February 15, 2019″

これは去年、Sydney Morning Heraldに載っていた記事ですが、
私もここメルボルンで同じような記事を読みました。というか、
この記事を読んで、妙に、納得するものがありました。
というのは、結構、ご父兄の中に、
大人として生活するうえで問題のない読み書きができるレベルにない方が多い?!と
肌感で感じているからです。
読み書きができない理由としては…
⋆正規な学校教育を受けてこられなかった
⋆ディスラクシア(dyslexia)などの学習障害がある
⋆失読症、難読症、識字障害などの理由がある
⋆または、単に移民者で英語が第二か国語となるため、読み書きができない。または自信がない。など数々の理由が挙げられます。
読み書きができないことを隠している大人も多い
幼稚園でご父兄と身近に接していく中で、度々、
書類などの提出物、アンケート、お便り、市役所からの公的なメール通信などのやり取りが出てきます。
 Miku
Miku”OOのアンケートまだ提出されていないようですが、今、ここで書いていかれますか?”



「ああ、今度にします。」
「家のPCが壊れていて、まだ読んでいません」
「あれ?おかしいな受け取っていませんが、
どんな内容のものでしたっけ?」
などが、頻繁に出てきたら、忘れていたり、だらしがないお母さんなのではなくて、
”何らかの理由で、読み書きができない、お便りを理解できない”
と、判断して、それ相応の対応をしてあげることが、大事だと思います。
決して、そのお母さんに恥をかかせたりさせないよう、細やかな気配りで、他の人がいないところで、



「一緒にここで書いていきましょうか?」
「OOていうような内容のメールが市役所の方から来ていましたが、
ここに印刷しておきました」と言いながら、内容を口頭で確認する。
「このアンケートに回答が必要とされるのですが、
ご自宅のPCの調子が悪いようなら、代わりに回答-もちろん本人の意向を重視 - 園のiPadから一緒に出しましょうか?」 などなど
私の目の前で、震える手でペンをもってサインしようとしたり、
目が悪くて読めないふりをしたり、時間がないから書けない、
そしてもっとひどいと、学校時代を思い出すのか、’こんな書類、何回出せばいいの?’など、
自分の識字障害を隠したいがゆえに、攻撃的になる人もたまーにいます。
でも、こうして本人の自尊心を守りつつ、あくまでも、
私は助っ人になりますよ、心配しないでいいですよ。
という対応を笑顔と一緒に実践すると、
必ず、相手のお母さんも、安心して心を開いてくださる日がくるのです。
相手のニーズに合わせてご父兄とパートナーシップを築く


幼稚園の先生の仕事は、子供の発達と成長を支えることですが、
同時に、子供の第一の教育者となるご父兄の信頼をえて、その家族、
子供の住んでいる環境全体を把握しながら、関わっていくことが
大部分を占めます。
子供が一番長い間過ごしている環境は、家庭です。
その、家庭のご両親から、信頼、任せても大丈夫という安心感をもらえたら、
ご父兄とのパートナーシップが確立できたも同然です。
そして、そのパートナーシップを築けるかどうかが、
子供の成長を総括的に見ていけるかどうかの鍵になります。
私は、このパートナーシップの確立を、とても大事にしています。
”この先生に、園に大事な子供を安心して預けられる”という気持ちがあってこそ、園側とご父兄の意思疎通もうまくいくし、何らかの問題が起こったとしても、
こじれることなく、話せばわかってもらえる関係になるのです。
ご父兄と日々関わり、話を聞いていく中で、
家庭環境の実態がまざまざと浮かび上がることがよくあります。
ご父兄が隠そうと思っていても、子供との会話、子供の行動、遊び方、
そしてご父兄の態度の中から、教育を受けてきていない事、家庭内暴力の問題、メンタルヘルスの問題、
家族の誰かの病気、経済的な問題などが、思いもかけず見えてくることがあるのです。
コミュニケーションとして、その問題を感じたとき、こちらに少しでも ”偏見”があると、
相手は臆病なウサギのようにさっと、距離をおいて逃げて行ってしまいます。
たとえ、その問題に気が付いて「ええ~、そんなことが起こっているなんて」と思ったとしても、
平静を保ち、じっと変わらぬ態度で、相手の話を聞いて、
必要があれば手助けしますという姿勢で接することが大事だと、私は経験から感じています。
問題解決に向けて、相手のニーズを無視して、押しつけがましい態度をとるのでなく、
”ただ誰かに胸の内を聞いてほしかった”ということもあるので、
そこは、じっと我慢強く、相手の話に耳を傾けて、聞くように努力しています。